第1回 妊娠中の貧血の検査 (シリーズ妊婦健診の血液検査・尿検査)
このシリーズでは、冒頭で妊娠によって母体に起こる生理的な変化の例を挙げ、そこに妊婦健診の検査項目を関連付けながらご紹介していきます。妊娠中は非妊娠時と比べて体内のバランスが大きく変化しているにも関わらず、検査の説明文が一般的な内容にしか触れていなかったり、検査値の基準範囲が妊婦を対象にしたものでなかったりと戸惑うことがあるかもしれません。妊婦さんが検査結果を見る際の一助になりましたら幸いです。
第1回 妊娠中の生理的変化① 貧血になりやすくなる
1. 貧血とは ~ 母体や胎児に悪影響をもたらす ~
貧血になるとめまいやだるさ、息切れといった様々な症状が現れますが、これらの症状は体内の酸素が不足することで起こります。例えば、めまいは脳の酸素不足、だるさは筋肉の酸素不足によって引き起こされ、息切れは呼吸の回数を増やして酸素を少しでも多く取り込もうとして起こります。呼吸を少し長く止めた後にどのような症状が出るかを想像すると理解しやすいかもしれません。
このように酸素は体の機能を維持するために欠かせないエネルギー源であり、貧血によって酸欠状態が続くと母体だけでなく胎児にも悪影響をもたらします。そのため妊婦健診では定期的に貧血の検査を行います。

2. 貧血の検査 ~ ヘモグロビンの値をみる ~
酸素は赤血球に含まれるヘモグロビンというタンパク質によって全身に運ばれており、このヘモグロビンが減って十分な酸素を運べなくなると貧血が引き起こされます。そのため貧血を検査する際は、血液検査でヘモグロビンの濃度を調べます。ヘモグロビン濃度は血算と呼ばれる検査の一部で、検査結果に「Hb」や「HGB」のような略称で記載されていることもあるので探してみてください。
妊婦のヘモグロビン濃度の値を見る際は、次に述べる生理的水血症という現象を考慮する必要があります。
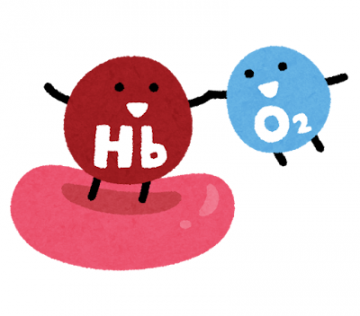
3. 生理的水血症 ~ 妊娠中は血液が薄まる ~
妊娠中は血液が薄まってヘモグロビン濃度が下がることが知られています。血液中の水分量は妊娠後から徐々に増えていき、妊娠後期(28週以降)には妊娠前と比べて約50%も増加します。水分の増加に反応して赤血球も緩やかに増えますが、全体として血液は薄まっていきます。この血液が薄まる現象は、血液の粘度を下げることで子宮や胎盤に血液を送りやすくしたり、血栓を予防したりするための反応と考えられており、生理的水血症と呼ばれています。
この生理的水血症では血液が薄まってヘモグロビン濃度は下がるものの、ヘモグロビンの量は一定以上に保たれるため病的な貧血とは区別して扱う必要があります。
以下に妊婦のヘモグロビンの検査についてまとめます。
| 妊婦健診項目① ヘモグロビン(HGB、Hb) |
|---|
| 血算という検査に含まれる項目で、血液中に含まれるヘモグロビンの濃度を表します。 (結果例)HGB 11.6 [g/dL] 血液が運搬できる酸素の量の指標となり、妊婦健診では主に貧血を探るために検査します。生理的水血症により血液が薄まることも考慮し、WHOの基準では妊婦の貧血を11.0 g/dL未満(特に妊娠中期は10.5 g/dL未満)と定義しており、その値は非妊婦(12.0 g/dL未満)よりも緩く設定されています。 |
一方、次に述べる鉄欠乏性貧血ではヘモグロビンが十分に作られなくなるため、ヘモグロビンの濃度だけでなく量も減少します。妊娠中に起こる貧血のほとんどが鉄欠乏性貧血によるものです。
4. 鉄欠乏性貧血 ~ 体内の鉄が不足する ~
ヘモグロビンは内部に鉄を含んでおり、この鉄が酸素を結合したり放出したりすることで全身に酸素を届けています。材料となる鉄が不足するとヘモグロビンが十分に作られなくなるため貧血に至ります。この鉄が不足して起こる貧血を鉄欠乏性貧血と言います。
妊娠中は週数が進むにつれて母体や胎児、胎盤などが必要とする鉄の量が増えていきます。特に妊娠中期以降(16週以降)は妊娠前の2~3倍の量の鉄が必要となるため、鉄欠乏性貧血を起こしやすくなるので注意が必要です。
妊娠中は週数が進むにつれて母体や胎児、胎盤などが必要とする鉄の量が増えていきます。特に妊娠中期以降(16週以降)は妊娠前の2~3倍の量の鉄が必要となるため、鉄欠乏性貧血を起こしやすくなるので注意が必要です。
5. 鉄が不足するまでの過程 ~鉄不足は静かに進行し、すぐには回復しない~
人は鉄を効率よく利用するために臓器に鉄を蓄えておく仕組みを備えています。この蓄えられた鉄は貯蔵鉄と呼ばれ、鉄が不足した場合には貯蔵鉄から払い出すことで貧血を防いでいます。
貯蔵鉄が存在するおかげで鉄の供給不足が生じても体内の鉄はすぐには不足しないため、次のような過程を経て鉄欠乏性貧血に至ります。
① 正常な状態 (十分な量の貯蔵鉄が存在する)
② 鉄欠乏状態 (貯蔵鉄が消耗していき、やがて枯渇して、鉄の欠乏が生じる)
③ 鉄欠乏性貧血 (鉄の欠乏によりヘモグロビン濃度が下がる)
鉄欠乏状態は自覚することが難しく、気付かないうちに進行していることがあります。特に妊娠前から月経や食事制限などによって鉄欠乏状態が進行していると、妊娠中に鉄欠乏性貧血を起こしやすくなります。
貯蔵鉄が存在するおかげで鉄の供給不足が生じても体内の鉄はすぐには不足しないため、次のような過程を経て鉄欠乏性貧血に至ります。
① 正常な状態 (十分な量の貯蔵鉄が存在する)
② 鉄欠乏状態 (貯蔵鉄が消耗していき、やがて枯渇して、鉄の欠乏が生じる)
③ 鉄欠乏性貧血 (鉄の欠乏によりヘモグロビン濃度が下がる)
鉄欠乏状態は自覚することが難しく、気付かないうちに進行していることがあります。特に妊娠前から月経や食事制限などによって鉄欠乏状態が進行していると、妊娠中に鉄欠乏性貧血を起こしやすくなります。
鉄欠乏性貧血の状態まで進行すると、治療には長い時間が掛かります。鉄剤を飲み始めてもヘモグロビン濃度はすぐには上がらず、一般にヘモグロビン濃度が元に戻るまで数週間、貯蔵鉄が十分な量に戻るまで数か月の時間を要します。そのため鉄欠乏性貧血を発症する前の段階からバランスの良い食事を心がけ、鉄の摂取量を確保することが重要です。
6. 貧血が母体や胎児にもたらす影響
最後に妊婦の貧血と関連性が指摘されている事項を列挙します。これらは様々な要因によって引き起こされますが、貧血による酸素不足や鉄不足などがその一因となる可能性があります。
母体へのリスク
- 分娩時の出血量の増加
酸素不足によって子宮の収縮力が低下すると出血が止まりにくくなります。 - 分娩後に輸血が必要となるリスクの増大
妊娠中に貧血が進行している場合は、分娩時の出血の影響が加わることで重度の貧血状態となり、輸血が必要となる場合があります。 - 産後うつ
産後貧血が産後うつのリスクを高める可能性が示されています。
胎児へのリスク
- 胎児発育不全(在胎週数に対して胎児の発育が十分でない状態)
- 早産(妊娠37週未満での出産)
- 低出生体重児(出生体重が2,500g未満)
- 神経系の発達への影響 鉄は胎児の神経系の発達に重要です。通常、母体の鉄が不足していても優先的に胎児に鉄が届けられますが、重度の不足の場合はその仕組みが働かなくなることが示唆されています。
- 胎児の鉄貯蔵不足 出生後しばらくしてから鉄が欠乏し、貧血を発症する場合があります。
(参考文献)
- UK guidelines on the management of iron deficiency in pregnancy
(参考)その他の貧血の指標として用いられる検査項目
ヘモグロビン濃度以外にも貧血の指標となる検査項目があり、その一部を以下で紹介させて頂きます。興味のある方は検査結果と合わせてご確認ください。
以下はヘモグロビンと同様に血算という検査に含まれる項目です。
① ヘマトクリット値(HCT、Ht)
血液は血球成分と液体成分に分けられますが、その血球成分の割合をヘマトクリット値と言います。赤血球の数や大きさ、液体成分の増減などが反映されるため、妊婦では水血症により低値傾向を示し、さらに貧血では赤血球が減ることで低値となります。
ヘマトクリット値も貧血の診断に用いられ、WHOの基準では妊婦は33%未満(特に妊娠中期は32%未満)を貧血と定義しています。(非妊娠時は36%未満)
ヘマトクリット値も貧血の診断に用いられ、WHOの基準では妊婦は33%未満(特に妊娠中期は32%未満)を貧血と定義しています。(非妊娠時は36%未満)
② MCV(平均赤血球容積)
赤血球の平均的な大きさを表します。鉄欠乏性貧血では赤血球のサイズが小さくなるため、通常MCVは80 fL未満になるとされます。ただし妊娠中に鉄欠乏性貧血となった場合は正常サイズの赤血球と小型化した赤血球が混在することにより、しばしば80 fL以上に保たれることがあります。
日本鉄バイオサイエンス学会では、妊娠9週以降についてMCV 85 fL未満かつヘモグロビン 11.0 g/dL以上を「鉄欠乏状態」、MCV 85 fL未満かつヘモグロビン 11.0 g/dL未満を「鉄欠乏性貧血」と定義しています。
日本鉄バイオサイエンス学会では、妊娠9週以降についてMCV 85 fL未満かつヘモグロビン 11.0 g/dL以上を「鉄欠乏状態」、MCV 85 fL未満かつヘモグロビン 11.0 g/dL未満を「鉄欠乏性貧血」と定義しています。
以下は鉄についての検査項目です。妊婦検診で検査するかどうかは各施設の判断となります。
① 血清フェリチン
血液中のフェリチンと呼ばれるタンパク質の濃度を調べます。フェリチンは貯蔵鉄の一種で、臓器から血液中に流れ出たフェリチンの濃度を測定することで貯蔵鉄がどれだけ存在するかを推定することができます。
ただし、炎症があると高値となり、妊娠中は血液の希釈の影響を受けるほか、水血症に伴って増えた赤血球に含まれる鉄の量は反映しないため妊娠週数が進むほど体内の鉄の実態と乖離するといった問題があります。また他の検査項目と比べて測定コストが高価です。
WHOの基準では妊娠12週までに血清フェリチン15ng/mL未満の場合を鉄欠乏と定義しています。
ただし、炎症があると高値となり、妊娠中は血液の希釈の影響を受けるほか、水血症に伴って増えた赤血球に含まれる鉄の量は反映しないため妊娠週数が進むほど体内の鉄の実態と乖離するといった問題があります。また他の検査項目と比べて測定コストが高価です。
WHOの基準では妊娠12週までに血清フェリチン15ng/mL未満の場合を鉄欠乏と定義しています。
② 血清鉄(Fe)
血液中を運搬されている鉄の濃度を表します。貯蔵鉄が枯渇すると血清鉄は低値となるため、鉄の欠乏状態を反映します。
ただし、炎症によっても低値となり、日内変動も大きく(一般に朝に高く、夜に低い)、さらに妊婦では血液の希釈の影響を受けるといった問題があります。他の検査結果と合わせて評価します。
ただし、炎症によっても低値となり、日内変動も大きく(一般に朝に高く、夜に低い)、さらに妊婦では血液の希釈の影響を受けるといった問題があります。他の検査結果と合わせて評価します。
③ TIBC(総鉄結合能)
血液中にはトランスフェリンと呼ばれる鉄と結合して鉄を運搬するタンパク質が存在します。TIBCはこのトランスフェリンが結合できる鉄の総量を表します。鉄が不足するとトランスフェリンが増加することからTIBCは高値となります。
ただし、妊婦では血液の希釈の影響を受けて高値傾向となるほか、妊娠中期以降にはトランスフェリンが生理的に増加して高値になるといった問題があります。他の検査結果と合わせて評価します。
ただし、妊婦では血液の希釈の影響を受けて高値傾向となるほか、妊娠中期以降にはトランスフェリンが生理的に増加して高値になるといった問題があります。他の検査結果と合わせて評価します。
検査課 伊豆田

